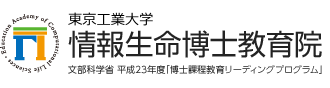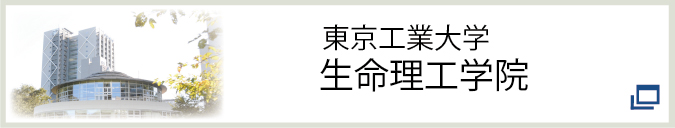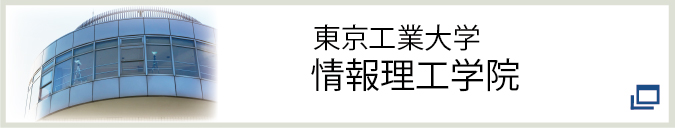教員・学生の声 黒川 裕美子、松崎 由理、ヨビッチ ドラゴミルカ

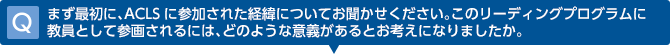

黒川:東工大で次世代シークエンサ演習を担当する教員を募集している、という公募を見たのが参加のきっかけです。内容を見た時に、私にピッタリだと思いました。
私の研究テーマは、ゲノムの安定性の維持機構の解析です。ちょうどゲノム周辺の解析で次世代シークエンサの解析というのが流行っていた時期で、「自分もやってみたいな」という思いがありました。演習を通して自分も学べ、研究にプラスになるだろう、と。
また、自分が研究してきたDNAやゲノムの解析技術や知見が、学生の演習にも役に立つとも考えました。もともと教えることに興味もあったので、良いチャンスだとも思いました。
ヨビッチ:私は東工大に留学して、修士/博士後期課程を修了しました。学生の頃、公的機関での1ヶ月間のインターンシップが義務づけられていて、理研の研究室でインターンシップを行いました。インターンシップを終了した後、理研の先生がもうちょっと理研で研究を続けてみないかと誘ってくださいました。東工大の研究室の先生と理研の先生の教え方は違っていましたが、先生方の若者に科学への好奇心を育ませる方法がとても印象的でした。その時、学生にとって先生の存在はとても重要であり、分野が異なる人とのコンビネーションによって得られた知識は学生を成長させると思いました。
その後、生命科学と情報科学の学生を教育する新しいプログラムが始まることを聞き、研究室と理研にいた頃に学んだ、異なるスタイルのアプローチを合わせた経験を思い出しました。生命または情報の先生が、情報または生命を専攻する学生に教えるのはおもしろそうだと思い、参加を決めました。
松崎:大学院では生命現象の数値シミュレーションが研究テーマでした。東工大に移ってからは、スーパーコンピュータを使ってタンパク質間の相互作用を研究していました。このプログラムに参加した理由は、自分が研究する過程で苦労してきたことが生かせる、と思ったからです。別分野の人と協力して一つの問題に取り組むことの良さと難しさ、どちらも経験しています。それを学生に伝えられると考えました。


黒川:まず、教えることへの不安はありました。それまでずっと教育ではなく専門分野の研究だけをやってきたからです。ただ、もともと、「人に分かりやすく伝える」「人がどう受け取るか」ということにも興味がありました。異分野同士の教育という難しさは、単に教科書内容を伝える教育とは違います。そこが私にはむしろ面白さに感じました。複数の“やりたいこと”が出てきて、研究/教育それぞれにかける時間は減るかも知れないけれど、学生と一緒に学べる良いチャンスだと考えたのです。趣味と実益、と言えるかも知れません(笑)。楽しみながら取り組むことで、ステップを上がれると考えています。
ヨビッチ:最初は、情報系の学生に教えるのは少し心配でした。ただ、実際に始めてみると、難しかったのは第1回目の授業だけでした。学生たちは最初、とてもシャイで、コラボレーションが少ししかできませんでした。けれども次の日になると徐々にコラボが進み始めて、最終日には全て一緒に行うことができました。とても嬉しく思うと同時に、それまで持っていた不安も払拭できましたね。
松崎:私はこれまでの研究の過程で、必要なソフトウェアを作り、それを改良するために多くの方に使ってもらう機会−チュートリアル、ワークショップなど−がたくさんありました。バックグラウンドの異なる方を集めて何かを伝えるということは初めてではなかったので、大きな不安はありませんでした。また、大学院時代の経験から、専門分野が一つではない、という中で学生が何を不安に思ったりするかということが、ある程度分かっています。これまで、類似した状況で友人や先輩と話してきたことを思い出しながら、学生に接しています。学生の性格は様々ですし、時代の移り変わりもあるので、単純に自分の考えを適用することはできませんが、学生とのやり取りの中で自分の考えが変わっていくこともあり、面白いです。


黒川:確かに、夏の学校は変わりましたね。最初の頃は各自が持ち込んだ研究がテーマで、開催前に「こんな結果が出るんじゃない?」というのを予測できる、ある程度やりやすいテーマでやっていた気がします。それが徐々に、もっと現実的なテーマになってきました。
松崎:以前だと、一つの分野−たとえば「タンパク質の構造と機能」や「ゲノムと染色体のダイナミクス」など−を選んでテーマにしてきましたが、昨年(2016年)は趣向を変えて実施してみることにしました。
国連本部のあるニューヨークが開催地だったので、その地ならではのテーマを設定しました。2015年に国連が発表した『Sustainable Development Goals(持続可能な発展のための目標, SDG)』というもので、食糧、健康、衛生など、生命科学も貢献できる様々な分野について、2030年までに達成すべき具体的な目標が掲げられています。平和な世界を実現するために人々が動く力をつけるには、まずこれらの問題が改善される必要があるという考えで設定されました。「国連が発表したゴールを達成するために必要な研究を計画する」という課題のグループワークを柱とし、国連本部でSDGについての展示を見学し、講義を受けました。学生は適応力が高いので、「ふだん考えていないテーマをもらって困った」ではなくて、逆に「発想の幅が広がった」という感想が多く出ました。
黒川:国連とのコラボ、というのを聞いた時には、「とても斬新だな」と思いました。ACLSでないとできないテーマだな、とも。所属する研究科などで夏の学校、研究のコラボの発表会、グループワークをやりましょう、といった時には、たぶん出てこない発想だと思います。オリジナリティがあり、社会に直結するようなグローバルな問題を考えるという点では、「すごく発展したな」と思っています。
テーマだけでなく、企画や運営の方法も毎年レベルが上がっています。学生が企画/運営に参加するわけですが、最初の頃は本当に決まり切った最低限の内容、たとえば学会とか研究集会をやるにはこういうことが必要だろうと準備していたのですが、今は国際学会レベルのきちっとしたものの上に様々な企画を盛り込んだ形になっています。私たちを含め、スタッフも大変ですが(笑)、本当にレベルが上がったと思います。
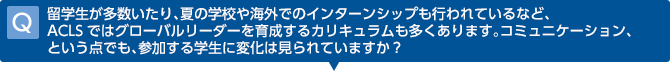

ヨビッチ:ACLSで開催する「グローバルコミュニケーションコンテスト」というイベントがあり、第1回目から関わってきました。最初の時に比べると、発表者として参加する学生がだいぶ変わってきています。第1回目の時は、学生が手を挙げてくれるかどうかが心配でした。そのため、イベントの趣旨や内容をしっかり説明する必要がありました。そこを成功させることができたので、2回目からは多くの学生が参加するようになりましたね。
黒川:最初の頃は留学生が結構手を挙げてくれましたが、最近は日本人が手を挙げます。半年しか授業を受けていない学生が積極的に参加したり、学生がコミュニケーションに対する自信を持ってきたようですね。
松崎:ACLSでは、“勉強としての英語”ではなく、“目の前にいる人と協働するための言葉”を学ぶ環境を用意しています。留学生と議論しないと進まない……という環境になっているので、英語を使う時の姿勢が変わるんだろうな、と思っています。
ヨビッチ:担任メンターとして日本人の学生と接する時、始めは日本語で話します。そして、ステップ・バイ・ステップで、英語で話す頻度を高めていきます。学生がコミュニケーションクラス→グローバルコミュニケーションコンテスト→海外インターンシップと体験したら、もう後はすべて英語で話すようになります。インターンシップから帰ってきた学生からは「もう大丈夫なので会話は全部英語でお願いします」と言われますね(笑)。海外インターンシップを経験できることは、とても意義があります。海外で3ヶ月間、一人で過ごすわけですから。
黒川:そういった経験を通して、英語で話すということへの緊張感が薄れるんでしょうね。

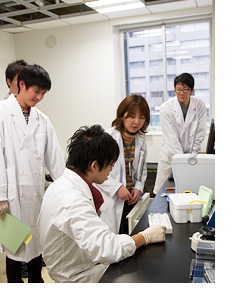
黒川:担任メンターとして、いまは各自が9〜10人くらいの学生を担当しています。最初の頃に比べると、学生の意識が結構変わった、と感じます。研究室の先輩がACLSに参加しているなど、周りの様子を見て、ACLSがどんなものなのか分かった上で入ってくる学生が多くなってきています。以前は「何かいろいろなことが学べるらしい」と漠然と考えている学生が多かったですが、最近はある程度ACLSを理解したうえで敢えて入りたいという学生がいますね。
松崎:計算機の性能向上、実験手法の進歩など、授業で教えられる/研究で使えることも変わってきました。変化翻弄されず、本質を見抜くにはどうすればよいか?自分でもしっかりとした答えを持てない時は、学生に相談することもあります。立場に関係なく、互いの持つものを出し合えるような関係を作れたらよいなと思っています。
黒川:学生の本質− Γ の太い方の部分−には口を出さず、そこから出ている枝の部分を多く、大きくつけてあげることに重きを置いています。新しい技術が出てきた時も、枝を一本つけるだけでいい。「いままで培ってきた、学んできたことは、そのまま大事に太く伸ばして下さい」と接しています。学生が変わっても、そこは変えていないです。
ヨビッチ:ACLSは、英語で表現すれば「Super Guided Program」です。学生をきちんと導くための環境を整えています。ACLSでは、リーダーシップやビジネス能力を伸ばすイベント、インターンシップなどのプログラムで、良い意味で「強制的に」コミュニケーションをとる機会を提供してきました。学生たちは、科学を普段と別の角度か見られるこのような経験を歓迎しています。
松崎:特任教員だけではなく、専門性の高い常勤の先生達がプログラム全体をしっかり見てくれているのも大きいと思います。たとえば夏の学校の企画なども、学生が表面的に考えて出してきた時に、するどく見抜いて批評してくれる。そういった場所も用意して、学生が基本的なところから自分で考えるよう促そうとしています。


黒川:私たち教員も、学生も、これまでチャレンジしながらACLSというプログラムを続けてきました。今ある形は最初から出来上がっていたわけではなく、まさに“走りながら作り上げて”現在のようになっています。私たちは生命と情報のΓ、ということでやってきましたが、他の分野−例えば人文系や社会学系との融合など−でも参考になる部分や通用する部分があると考えています。そのためのモデルケースにしてもらえると嬉しいな、と思います。
松崎:ふだん、ずっと一人で考えているような人にも来てほしいと思います。ある問題について、一人で長期間考えることは必要なプロセスです。けれども、今は社会の状況が変わってきていて、みんなで一緒に取り組まないとできないようなことがたくさんあります。ですから、一人で考える学問志向の強い人にも思い切って来てもらうことによって、やり方を広げてほしいし、周りの学生の刺激になってほしいな、という期待があります。
ヨビッチ:将来、アカデミックな世界に残ろうと、産業界に出て行くことになろうと、自分自身が行っていることの特徴(他のものとの違い)を示すことは重要です。ACLSでは、その違いを学ぶことができます。ACLSで学生がしている“違いの見せ方”は、リーダーシップにしても英語でのコミュニケーションにしても、本当に小さなスタートです。その小さなものを大きな変化にしていくためのトレーニングがACLSなのです。
確かに、学生はACLSでたくさんのことをしなければならず、タフでハードなところもあります。けれども、それをやり抜くことによって得られるメリットはとても大きなものです。学生が正しく自分の方向性を設定するためには、さまざまな面での指導が必要です。私たちが提供しているコースやトレーニングを通して、自分たちを形作ったり、自分がどういう方向性に行くか、ということは、いろいろな経験をすることによって決めやすくなります。ACLSで学んだ5年を経過した後でこそ「ああ、この道が自分にフィットしている」と気づくような。そんな可能性を提供しています。
黒川:学生は、自分で自分をプロデュースしている途中だと思います。学生自身はそれに気づいていないことが結構多くて、たとえば学生が何かのイベントで「自己アピールして下さい」と言われた時に、シンプルに研究室の研究のことしか言わなかったりするんです。そうではなくて、ACLSでの経験が絶対自分の武器になるわけで、それをもっと自分の武器としてアピールできたらいいな、と思っています。ACLSでは、グローバルコミュニケーション、海外インターンシップでの経験など、自分の武器になるアピールポイントを持つ手助けをたくさん用意しています。ぜひ活用してもらえればと思います。
※掲載内容は2016年12月のインタビュー時点のものです。